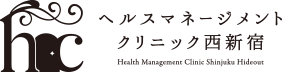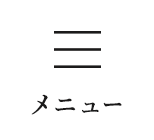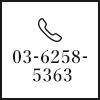糖尿病と食後高血糖の関係をできるだけわかりやすく解説
はじめに
糖尿病は日本における代表的な生活習慣病であり、患者数・予備軍を含めると2,000万人以上と推定されています。
中でも注目されているのが 「食後高血糖」 です。
健診で空腹時血糖は正常でも、食後の血糖値が大きく上昇するケースがあり、これが心血管疾患リスクや糖尿病発症につながることがわかってきました。
この記事では、糖尿病と食後高血糖の関係、血糖値の種類や意味、血糖変動とインスリンの仕組みについて、一般の方にも理解しやすく解説します。
血糖値とは何か
血糖値とは、血液中のブドウ糖(グルコース)の濃度を指します。
食事から摂取した炭水化物は消化吸収されてブドウ糖となり、血流にのって全身に運ばれます。ブドウ糖は脳や筋肉などのエネルギー源として不可欠です。
ただし、血糖が高すぎても低すぎても体に悪影響があるため、体は常に一定の範囲に調整しようと働きます。その調整の中心的な役割を果たすのが インスリン です。
血糖の種類と意味
1. 空腹時血糖
-
10時間以上絶食した状態で測定
-
基準値:70〜99 mg/dL
-
100〜125 mg/dL → 境界型(糖尿病予備軍)
-
126 mg/dL以上 → 糖尿病の疑い
空腹時血糖は肝臓での糖の産生と、インスリンの基礎分泌のバランスを反映します。
2. 食後血糖
-
食後2時間前後に測定
-
基準値:140 mg/dL未満が正常
-
140〜199 mg/dL → 境界型
-
200 mg/dL以上 → 糖尿病の疑い
食後血糖は、食事による糖の吸収と、それに対するインスリン分泌の応答を反映します。
「食後高血糖」はインスリンの分泌が遅れたり不足したりすることで生じます。
食後高血糖の何が問題か
食後高血糖は、空腹時血糖が正常でも見過ごされることがあります。
しかし、以下のようなリスクがあることが知られています。
-
動脈硬化を促進:食後の血糖急上昇は血管内皮にダメージを与え、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めます。
-
糖尿病の早期兆候:空腹時は正常でも、食後高血糖が続けば糖尿病発症に進展する可能性が高いです。
-
酸化ストレスや炎症反応:血糖の急上昇と下降が繰り返されることで、体に負担がかかります。
そのため、近年は健診でも 75gブドウ糖負荷試験(OGTT)が用いられ、食後高血糖を早期に発見する取り組みが広がっています。
血糖変動とインスリンの仕組み
血糖の上がり下がりはインスリンの分泌と密接に関係しています。
健常者の流れ
-
食事で血糖上昇
-
膵臓からインスリン分泌
-
筋肉・肝臓・脂肪組織でブドウ糖が取り込まれる
-
血糖値が再び安定
糖尿病や予備軍の場合
-
食事摂取後の血糖上昇からインスリン分泌までに遅れが発生する
- 血糖が高い状態の持続時間が長くなってしまう
-
血糖上昇に合わせて必要なインスリンが分泌されるがその効きが悪い(インスリン抵抗性)
→ したがって、血糖値のスムーズな安定化が図れず、食後血糖が高止まりする - 血糖時が高い時間帯が長くなっていくため、その悪影響が全身の血管を始め、様々な
臓器に引き起こされる。 - 腎臓の血管に障害を受けると腎不全状態
- 目の網膜の血管に障害を受けると網膜症、網膜出血
- 四肢末梢の血管が障害を受けると血流不全が起こり傷が治りにくい、化膿しやすいなどの
状態が起こり、壊疽、切断の危険性がある
食後高血糖の改善のために
食事の工夫
-
野菜から先に食べる「ベジファースト」
-
炭水化物の量を調整
-
食物繊維やたんぱく質を組み合わせて吸収をゆるやかに
運動の工夫
-
食後30分以内に軽いウォーキング
-
筋肉を使うことで糖が取り込まれやすくなる
医療のサポート
-
HbA1cや血糖変動の検査(持続血糖測定CGMなど)
-
必要に応じて薬物療法(α-グルコシダーゼ阻害薬、GLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬など)
まとめ
-
空腹時血糖だけでなく、食後高血糖が糖尿病や動脈硬化リスクに大きく関わる
-
血糖変動を知ることで、自分の体の状態をより正確に把握できる
-
食後高血糖が気になる人は、生活習慣改善と医療機関でのチェックが大切
西新宿・都庁前エリアで通いやすい立地にあり、仕事帰りやお買い物のついでにも立ち寄りやすいクリニックです。
糖尿病をはじめ、高血圧症、脂質異常症など生活習慣病全般の治療を行っておりますが、特に糖尿病治療に関しては院内検査機器も充実しており、診察当日に血糖値や糖尿病の状態をチェックすることが可能です。
<関連記事>
こちらもご覧ください
・糖尿病予備軍(糖尿病の危険性があると言われた人)のための専門外来
・血糖異常・糖尿病外来(当院の糖尿病治療方針の考え方)
・糖尿病院内検査7分で検査結果がでます【血糖値・HbA1c迅速即日検査】
・糖尿病の初期症状と受診の重要性|西新宿での受診をご検討の方へ
・糖尿病と食後高血糖の関係をわかりやすく解説
・糖尿病と食事療法|食べ方の工夫で血糖をコントロールする
・改めて糖尿病とは何なのか、分かりやすく解説します
・そもそも糖尿病って、何が問題なの?
・血糖値が高めと言われたら
・血糖値が高いと健診で言われても、そんなにショックを受けないでくだ